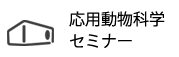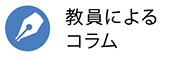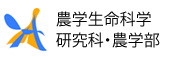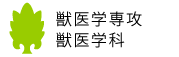応用動物科学専攻関連の研究室が公表した研究成果などです。
Publications from our Department.
(Google Scholar で見る / View at Google Scholar)
| ▼ 原著論文 / Original Papers | > 総説・図書など / Review etc |
|---|---|
| > 2024年 | |
| > 2023年 | |
| ▼ 2022年 (CLOSE) |
Essential amino acid intake is required for sustaining serum insulin-like growth factor-I levels but is not necessarily needed for body growth. Nishi H, Uchida K, Saito M, Yamanaka D, Nagata H, Tomoshige H, Miyata I, Ito K, Toyoshima Y, Takahashi SI, Hakuno F, Takenaka A. Cells 11(9):1523 (2022) 要求量を満たす必須アミノ酸の摂取は成長ホルモン(GH)の適切な活性発現に必要であり、給与条件によっては動物個体の成長に必須ではないことを示した論文です。動物細胞制御学研究室の修士課程修了生の長田悠加さん、朝重陽菜子さん、ポスドクの西宏起さん、東京慈恵会医科大学所属で動物細胞制御学研究室の研究生である齋藤真希さんの成果です。 こちらの解説もご参照ください。 NADPH-Oxidase Derived Hydrogen Peroxide and Irs2b Facilitate Re-oxygenation-Induced Catch-Up Growth in Zebrafish Embryo. Zasu A, Hishima F, Thauvin M, Yoneyama Y, Kitani Y, Hakuno F, Volovitch M, Takahashi SI, Vriz S, Rampon C, Kamei H. Front Endocrinol 13:929668 (2022) ゼブラフィッシュ胚の再酸素化誘発キャッチアップ成長において、NADPH-オキシダーゼ由来の過酸化水素とインスリン受容体基質(insulin receptor substrate; IRS2B)が重要な働きをしていることを示した論文。以前動物細胞制御学研究室でポスドクをしており、現在金沢大学の准教授である亀井宏泰さんの成果です Cooperative effects of oocytes and estrogen on the forkhead box L2 expression in mural granulosa cells in mice. Ito H, Emori C, Kobayashi M, Maruyama N, Fujii W, Naito K, Sugiura K. Sci Rep 12(1):20158 (2022) 動物のメスの正常な繁殖には、卵巣の体細胞が正常に分化して機能することが必須です。この論文では、卵巣体細胞の正常な分化制御に必須のFOLX2転写因子の発現がどのように制御されているのかを明らかにしました。FOXL2は卵巣腫瘍の原因因子としても知られ、本研究は女性不妊や腫瘍の原因解明につながることが期待できます。応動博士課程卒業生の伊藤さんらによる研究成果。 SOX17-positive rete testis epithelium is required for Sertoli valve formation and normal spermiogenesis in the male mouse. Uchida A, Imaimatsu k, Suzuki h, Han x, Ushioda H, Uemura M, Imura-Kishi K, Hiramatsu R, Takase HM, Hirate Y, Ogura A, Kanai-Azuma M, Kudo A, Kanai Y. Nat Commun 13:7860 (2022) ほ乳類の精子は精細管内で作られ、その中の管腔液の流れにより、セルトリバルブと呼ばれる弁様構造を経て精巣網(精巣基部に位置する網目状の管構造)へと運ばれる。本研究は、SOX17陽性の精巣網上皮が、隣接するセルトリバルブの形成とさらに「上流」の精細管の精子形成に必須であることを示した論文です。今年3月に卒業した獣医解剖学教室の内田あやさんの学位論文です。 日本語での研究紹介はこちら。 The effect of exposure on cattle thyroid after the Fukushima Daiichi nuclear power plant accident. Horikami D, Sayama N, Sasaki J, Kusuno H, Matsuzaki H, Hayashi A, Nakamura T, Satoh H, Natsuhori M, Okada K, Ito N, Sato I, Murata T. Sci Rep 12(1):21754 (2022) 1986年に起こったチェルノブイリ原子力発電所事故において、事故5年後に小児における甲状腺がんの発症率の上昇が報告されました。このことから、特に半減期が短く、甲状腺に蓄積する放射性ヨウ素(I131)が、甲状腺がんを起こすきっかけになるとの懸念がありました。このため、2011年に東日本大震災に伴って発生した福島第一原発の事故においても、周辺地域に飛散したヨウ素やセシウムといった放射性物質が、住民の健康や甲状腺の機能に与える影響について長らく懸念されてきました。 放射線動物科学研究室では、研究室の設立以来、「低線量の長期被ばくが生体に与える影響」の評価を行っています。約10年にわたり、福島第一原発事故の周辺(帰還困難区域)で現在も飼育されている牛を対象に、その外部被ばく量(空間からの被ばく量)、内部被ばく量(放射性物質を体内に取り込むことで受ける被ばく量)、身体の状態、甲状腺の形態、甲状腺の機能などをモニタリングしてきました。この度、これらの結果が論文にまとめられ報告されました。 2011年から2016年の間に、福島第一原発周辺の管理区域(帰還困難区域)で維持されている牛が受けた被ばく量は、推定1520 mGry:外部被ばく量が約1416 mGry、内部被ばく量が約 104 mGryでした。そのうち放射性ヨウ素(I131)からの被ばく量は推定85 mGyに及びました。ちなみに人において、1 Gry= 1 Svと簡易換算すると、日本における一般人の年間平均被ばく量は2.1 mGry (2.1 mSv)、5年間で10.5 mGryとなります。 これらの被ばく牛の甲状腺を調べたところ、他の一般牧場に飼育されている牛の甲状腺と比較して、重量がやや軽い傾向がみられました。また甲状腺の機能を維持するために必要な安定体のヨウ素I127の含有量も少ないことが分かりました。一方で病理学的な所見は見つかりませんでした。甲状腺機能の指標となる、血中の甲状腺ホルモン(T4)や甲状腺刺激ホルモン(TSH)の濃度を測定したところ、一般牛と比較して被ばく牛では高いことが分かりました。個々の牛を比較したところ、推定される被ばく量と甲状腺の変化には相関が認められませんでした。 *一般の牧場で人に管理され豊富な試料を与えられている牛と、管理区域内の山野で生活している半野生状態の牛では、栄養状態、運動量、自然環境から受ける変化や感染状態など、多くの点での違いがあり、正確に比較することはできない点はご理解ください。 事故により、不幸にも取り残された牛ですが、他の実験動物と比較して寿命が長く、10年にわたるモニタリングには適しています。また、除染されていない山野に広がる管理区域において、牛は年間を通して多くの草を食べるため、外部被ばくのみならず内部被ばくの評価にも適しています。一方で、大動物の管理は多くの労力と費用が必要であり、現地の多くの農家の方や、岩手大学、北里大学の先生方、寄付者の多大なる協力を得て、長期にわたる調査を行うことができました。また、放射性同位体の濃度測定は、東京大学のタンデム加速器研究施設の協力の下、行いました。 放射線動物科学研究室の堀上大貴さんと佐山尚也さんが中心になり、行った研究です。 N-Oleoyldopamine promotes the differentiation of mouse trophoblast stem cells into parietal trophoblast giant cells. Nishitani K, Hayakawa K, Minatomoto M, Tanaka K, Ogawa H, Kojima H, Tanaka S. BBRC 636:205-212 (2022) 胎盤が正常に機能するためには、適切な数の各種分化栄養膜細胞が、しかるべき位置に正しく配置されることが必要です。栄養膜細胞の分化運命決定機構に関する新たな知見を得ることを目的に、マウス栄養膜幹細胞(mouse trophoblast stem cell)を用いた低分子量化合物スクリーニングを行い、N-Oleoyldopamine (OLDA) が胎盤の最外層に分布するparietal trophoblast giant cellへの分化を促進させることを発見しました。OLDAは辛さ(痛み)や熱の受容体であるTrpv1のリガンドとして知られています。OLDAの作業機序の解明には今後の研究が必要ですが、本研究はマウス胎盤形成におけるTrpvの関与を示唆しています。応動博士課程修了生の西谷さん、応動出身の元特任助教・早川さんらによる研究成果です。 The Philippines stingless bee propolis promotes hair growth through activation of Wnt/β-catenin signaling pathway. TANG Y, WANG C, DESAMERO MJM, KOK MK, CHAMBERS JK, UCHIDA K, KOMINAMI Y, USHIO H, CERVANCIA C, ESTACIO MA, KYUWA S, KAKUTA S. Exp Anim 72(1):132-139 (2022) プロポリスは、ミツバチが木の芽や樹液、あるいはその他の植物源から集めたワックス(蜜蝋)です。フィリピン大学ロスバニョス校のMaria Amelita C. Estacio教授およびMark Joseph M. Desamero准教授(当研究室の博士課程修了生)との国際共同研究として、極めてユニークなフィリピン固有種のハリナシバチ(Tetragonula biroi Friese)から得られるプロポリスの発毛作用について機能性評価を行いました。単純剃毛処理したC57BL/6Nマウスに対して99.5%エタノールで抽出処理を行ったフィリピンハリナシバチプロポリスを塗布したところ、背部皮膚のメラニン色素沈着と毛包の組織学的解析により、プロポリスには毛包形成を刺激することにより発毛を促進していることがわかりました。さらに分子生物学的解析を行ったところ、ハリナシバチプロポリスはWnt/β-カテニンシグナル経路を活性化していることがわかりました。本研究により、フィリピンハリナシバチプロポリスは発毛作用をもつ新規の農産物として有望であることが示唆されました。 応用動物科学専攻・博士課程卒業の湯 玉蘭さん、王 辰さんおよび獣医病理学研究室、水産化学研究室の共同研究による研究成果で、Experimental Animals誌に掲載されました。 12-HETE promotes late-phase responses in a murine model of allergic rhinitis. Nakamura T, Tachibana Y, Murata T. Allergy 78(2):574-577 (2022) 花粉などの抗原の刺激に対して、くしゃみ・鼻水・鼻づまりの症状がでるアレルギー性鼻炎の患者数は急増しています。このアレルギー反応には抗原を認識したマスト細胞と呼ばれる免疫細胞が、ヒスタミンなどの炎症促進物質を大量に放出することで起こります。大量に放出されたヒスタミンは鼻粘膜の神経や血管を刺激してくしゃみや鼻水といった急性炎症反応を誘発します。しかし一方で、慢性化して患者を苦しめる”鼻づまり”については、その発症機構がよく分かっていませんでした。 放射線動物科学研究室では、マウスのアレルギー性鼻炎が慢性化したマウスの鼻汁中に、12-HETEと呼ばれる生理活性脂質が大量に産生されていることを発見しました。この脂質の病態生理活性を調べたところ、この脂質はアレルギー反応の成立に必須である2型ヘルパーT細胞の分化や鼻粘膜への浸潤、好酸球の鼻粘膜浸潤を促進するなどして鼻閉の症状を悪化させる作用を持つことを発見しました。また、12-HETEの合成を薬を用いて止めると、鼻閉の症状が緩和されることも発見して報告しました。 応用動物科学専攻・博士課程卒業の橘侑里さんと中村達朗元特任講師の研究成果であり、アレルギー分野のトップジャーナルであるAllergy (IF: 14.7)に受理・掲載されました。 A new species of the genus Sergentomyia França and Parrot (Diptera: Psychodidae) from Iriomote Island, Ryukyu Archipelago. Sanjoba C, Miyagi I. Med Entomol Zool 73(3):125-129 (2022) 琉球列島の西表島で新種のサシチョウバエ(ハエ目,チョウバエ科)を発見し、応用免疫学研究室の三條場千寿助教らが「Sergentomyia iriomotensis(新称和名:イリオモテサシチョウバエ)」と命名し報告しました。日本に生息するサシチョウバエとしては、S. squamirostris Newstead, 1923(ニッポンサシチョウバエ)に次ぐ2種目となります。 Leishmania infection-induced multinucleated giant cell formation via upregulation of ATP6V0D2 expression. Hong J, Sanjoba C, Fujii W, Yamagishi J, Goto Y. Front Cell Infect Microbio 12:953785 (2022) 寄生虫性疾患である内臓型リーシュマニア症の患者では、骨髄やリンパ節のマクロファージが多核化して、自己の赤血球が貪食する現象が見られます。今回、原虫感染誘導性の多核化にV-ATPaseの構成成分として知られるATP6V0D2が関与することを明らかにしました。Mφの多核化は病態形成にも関与することから、この分子を標的とすることで原虫の増殖と症状の両方を抑えるといった内臓型リーシュマニア症の新たな治療法につながることが期待できます。応動博士課程・洪さんらによる成果。 Urinary lipid profile of patients with coronavirus diseases 2019. Kida M, Nakamura T, Kobayashi K, Shimosawa T, Murata T. Front Med 9:941563 (2022) COVID-19の猛威は依然として収まっておらず、医療現場に過度な負担をかけない形での、適切かつ迅速、簡便な診断や治療方法の開発が望まれています。ウイルス感染などにより組織が障害をうけると、ダメージをうけた細胞の膜から生理活性脂質が産生され、これが炎症反応を引き起こします。つまり、体外に排泄される生理活性脂質の濃度を見ることで、体内で起こっている炎症の質や程度を評価することが可能になります。 放射線動物科学研究室の博士課程に所属する木田美聖さんと中村達朗特任助教(研究当時)らのチームは、COVID-19患者の尿中に排泄される約200種類の生理活性脂質の濃度を網羅的に測定した結果、健常な人の尿と比較して、患者の尿中には、炎症の誘発に関与するプロスタグランジンやトロンボキサンなどの代謝物が多く排泄されていることを発見しました。またこれらの一部は、すでに報告されている血中の炎症マーカーであるフェリチンの濃度とも相関することも分かりました。今後の引き続き研究が必要ですが、尿を用いた検査キットが開発できれば、家で簡便かつ迅速にCOVID-19症状の程度を評価することができるようになる可能性があります。 Role of landscape context in Toxoplasma gondii infection of invasive definitive and intermediate hosts on a World Heritage Island. Okada S, Shoshi Y, Takashima Y, Sanjoba C, Watari Y, Miyashita T. Int J Parasitol Parasites Wildl 19:96–104 (2022) 野生のイエネコとクマネズミにおける抗トキソプラズマ抗体保有状況から、トキソプラズマ原虫感染に影響する環境要因について明らかにしました。生圏システム学専攻・生物多様性科学研究室との共同研究による、獣医博士課程・所司さんらの成果です。 Urinary lipid production profile in canine patients with splenic mass. Kida T, Yamazaki A, Nakamura T, Kobayashi K, Yoshimoto S, Maeda S, Nakagawa T, Nishimura R, Murata T. J Vet Med Sci 84(11):1480-1484 (2022) 人と同様に犬や猫などの伴侶動物における病気の簡易かつ早期の診断方法の開発が求められています。本研究では犬の脾臓腫瘍の病態解明とバイオマーカーの探索を目的に、尿中脂質産生プロファイルを明らかにしました。 東京大学附属動物医療センターにて脾臓腫瘍と診断された犬から採取した尿を精製した後、検体中に含まれる脂質代謝産物を高速クロマトグラフィー・質量分析装置を用いて網羅的に解析しました。その結果、炎症反応を引き起こすプロスタグランジン(PG)E2の代謝物13,14-dihydro-15-keto-tetranor-PGE2、PGF2αやPGD2の代謝産物tetranor-PGFM、13,14-dihydro-15-keto-tetranor-PGD2などの尿中含有量が、犬の脾臓腫瘍の尿において健康な犬の尿と比較して有意に増加していました。 本研究成果は犬の脾臓腫瘍の病態生理の解明や、採血する必要なく脾臓腫瘍を診断できるバイオマーカーの開発につながる可能性があります。東京大学獣医外科の協力の下、卒業生の山崎さんと貴田さんが実験を行い、報告しました。 The strain of unfamiliar conspecifics affects stress identification in rats. Kiyokawa Y, Kuroda N, Takeuchi Y. Behav Processes 201:104714 (2022) ラットは、目の前にいるラットがストレスを受けているかどうかを識別できることが知られていました。しかしこの識別は、目の前にいるラットが自分と近しい系統でないと行えないことを明らかにしました。応動修士課程卒業生・黒田さんらによる成果。 Automated scratching detection system for black mouse using deep learning. Sakamoto N, Haraguchi T, Kobayashi K, Miyazaki Y, Murata T. Front Physiol 13:939281 (2022) C57BL/6マウスの引っ掻き行動を高精度で検出できる人工知能を開発しました。放射線動物科学研究室の学部生・坂本直観さんの研究成果です。人より正確に、実験者間や実験回差なく再現性と客観性の高い数値を得ることができます。企業での利用も進んでいます。 Mutations equivalent to Drosophila mago nashi mutants imply reduction of Magoh protein incorporation into exon junction complex. Oshizuki S, Matsumoto E, Tanaka S, Kataoka N. Genes Cells 27(7):505-511 (2022) キイロショウジョウバエのmago nashi変異体では、oskar mRNAの卵母細胞内での後極への局在化が失われます。この局在化にはスプライシング依存的にmRNAに結合するエクソン接合部複合体(Exon Junction Complex, EJC)が必要です。mago nashiタンパク質のヒトホモログであるMagohタンパク質に、ショウジョウバエで見出された2つの変異をそれぞれ導入し、in vitro結合実験やin vitroスプライシング反応系を用いて、EJC形成に与える影響を調べました。その結果、キイロショウジョウバエにみられる2つの変異は、別のEJC構成因子Y14への結合を弱め、細胞質に局在化してしまうか、EJCへの取り込みを低下させてしまうという現象を引き起こすことが明らかになり、EJC形成が正常に起こらない結果、oskar mRNAの局在化が起こらないことが強く示唆されました。応動修士課程の押月さんと日本学術振興会特別研究員の松本さんによる研究成果です。 Effect of fibroblast growth factor signaling on cumulus expansion in mice in vitro. Kanke T, Fujii W, Naito K, Sugiura K. Mol Reprod Dev 89(7):281-289 (2022) 排卵に必須の現象である「卵丘膨化」に対する卵巣内の線維芽細胞増殖因子シグナルの影響を解析した論文です。応動博士課程・菅家さんらによる成果。 Expression and regulation of estrogen receptor 2 and its coregulators in mouse granulosa cells. Emori C, Kanke T, Ito H, Akimoto Y, Fujii W, Naito K, Sugiura K . J Reprod Dev 68(2):137–143 (2022) 卵巣の正常な発達には卵母細胞由来の増殖因子と女性ホルモン(エストロゲン)が重要な役割を果たします。それらがどのようにかかわり合って卵巣発達制御をしているかについて研究した論文です。応動博士課程卒業生・江森さんらによる成果。 Comprehensive profiling of lipid metabolites in urine of canine patients with liver mass. Kida T, Yamazaki A, Nakamura T, Kobayashi K, Yoshimoto S, Maeda S, Nakagawa T, Nishimura R, Murata T. J Vet Med Sci. 84(8):1074-1078 (2022) 人と同様に犬や猫などの伴侶動物における病気の早期診断方法の開発が求められています。本研究では犬の肝臓癌の病態解明とバイオマーカーの探索を目的に、尿中脂質産生プロファイルを明らかにしました。東京大学獣医外科学研究室の協力の下、卒業生の山崎さんと貴田さんが実験を行い、まとめました。 The urinary lipid profile in cats with idiopathic cystitis. Takenouchi S, Kobayashi Y, Shinozaki T, Kobayashi K, Nakamura T, Yonezawa T, Murata T. J Vet Med Sci. 84(5):689-693 (2022) 下部尿路疾患は猫に非常に多い疾患であり、血尿、頻尿、排尿痛、尿しぶり、粗相などの症状によって動物と飼い主双方のQOLを低下させます。この猫の下部尿路疾患のうち、半数以上は原因不明の膀胱炎である「猫の特発性膀胱炎注」と診断されます。この疾患の、病態や原因はよくわかっておらず、その診断は他の疾患の除外に基づくものであるため、本疾患を他の疾患と区別して早く簡単に診断するためのバイオマーカーの開発が求められてきました。 放射線動物科学研究室では、猫の特発性膀胱炎のバイオマーカーの探索を目的に、尿中に排泄される脂質代謝物を、質量分析装置を用いて網羅的に解析し、プロスタグランジン(PG)類の代謝産物、PGF2αや15-keto-PGF2α、13,14-dihydro-15-keto-PGF2α、PGF3αの濃度が、健康猫の尿と比べ上昇していることを明らかにしました。こうした尿中脂質代謝物の濃度変化を見ることで、これまで診断が困難であった猫の特発性膀胱炎を早く、簡単に見つけることができる可能性があります。 Mapping of c-Fos expression in the medial amygdala following social buffering in male rats. Zhang X, Kiyokawa Y, Takeuchi Y.Behav Brain Res. 422:113746 (2022) ラットでは、ある特定の系統のラットが存在するとストレス反応が緩和される社会的緩衝という現象が知られています。相手のラットが特定の系統であるかを識別する際に、扁桃体内側核後腹部が関与していることを発見した論文です。 Social distancing measures differentially affected rats in North America and Tokyo. Kiyokawa Y, Tanikawa T, Ootaki M, Parsons MH.J Pest Sci. 95:79-86 (2022) 新型コロナウイルス感染症対策の一環として行われた緊急事態宣言やロックダウンが、東京都と北米のネズミに与えた影響を解析しました。その結果、東京都ではネズミ駆除業者の仕事に変化がなかった一方で、アメリカやカナダではネズミ駆除業者の仕事が増えたことが判明しました。清川准教授らによる研究成果。 An assessment of the spontaneous locomotor activity of BALB/c mice. Miyazaki Y, Kobayashi K, Matsushita S, Shimizu N, Murata T.J Pharmacol Sci. 149(2):46-52 (2022) 放射線動物科学研究室では、動画や人工知能を応用して実験動物の行動解析を自動化するとともに、人が見逃す表現型の検出できるシステムの開発を進めています。応動修士課程の宮崎優介さんらは、BALB/cマウスの自発運動を長期にわたって解析できるシステムを作り、雌雄差、週齢差、種差など今後の研究に必要な基礎データを収集し、論文にまとめました。 First detection of voltage-gated sodium channel mutations in Phlebotomus argentipes collected from Bangladesh. Sarkar SR, Kuroki A, Özbel Y, Osada Y, Omachi S, Shyamal PK, Rahman F, Kasai S, Noiri E, Matsumoto Y, Sanjoba C. J Vector Borne Dis. 58(4):368-373 (2022) 原虫性疾患である内臓型リーシュマニア症が流行しているバングラデシュでは、媒介昆虫のサシチョウバエに対しデルタメトリンによる防除が行われています。サシチョウバエのデルタメトリン抵抗性とその抵抗性に関与する遺伝子変異について明らかにした論文です。応動修士課程・黒木さんらによる研究成果。 The profile of urinary lipid metabolites in healthy dogs. Kida T, Yamazaki A, Kobayashi K, Nakamura T, Nakagawa T, Nishimura R, Murata T. J Vet Med Sci 84(5):644-647 (2022) 動物の疾患の診断や治療には人の診断薬や治療薬が用いられることも少なくありません。放射線動物科学研究室ではこれまで、尿を含む体液を用いたヒト疾患の診断技術を開発してきました。今回は「犬には犬の診断薬」を開発すべく、まず健康犬の尿中脂質代謝を明らかにし、報告しました。今後随時、各疾患特有の脂質代謝について明らかにし、疾患の診断や病態解明に応用していきます。卒業生の貴田大樹さんと山崎愛理沙さんの研究成果です。 Automated Grooming Detection of Mouse by Three-Dimensional Convolutional Neural Network. Sakamoto N, Kobayashi K, Yamamoto T, Masuko S, Yamamoto M, Murata T. Front Behav Neurosci. 16:797860 (2022) 実験動物として広く用いられているマウスやラットを含む多くの動物は、顔や体の毛づくろい(グルーミング)をします。グルーミングの頻度や長さ、対象部位は動物の心理的、身体的な状態を知るために有用な指標として知られています。実際に、ストレス刺激や、自閉症や認知症などの疾患により、そのパターンが変化することが報告されており、この評価が創薬の現場でも行われています。現在、多くの研究において研究者の目視によるグルーミングの評価が行われていますが、実験者の負担が大きく観察時間に限界があります。また、観察する人や環境によって実験結果が異なるため、客観性や再現性という点でも課題があります。 放射線動物科学研究室の坂本直観さんと小林幸司特任助教らは、AI(3次元畳み込みニューラルネットワーク)を用いて、動画からマウスの顔と体のグルーミング行動を自動判定する方法の開発に成功しました。本技術を用いれば、マウスのグルーミングを低コストで長時間、かつ自動的に検出できるため、画期的な成果です。これらの技術により高い再現性や客観性をもって動物の微細な心と体の変化を捉えられるようになると考えられ、動物実験の効率の大幅向上が期待されます。 15-hydroxy eicosadienoic acid is an exacerbating factor for nasal congestion in mice. Miyata K, Horikami D, Tachibana Y, Yamamoto T, Nakamura T, Kobayashi K, Murata T.. FASEB J. 36(1):e22085 (2022) 国民の3分の1近くが罹患する花粉症(アレルギー性鼻炎)。現在もその患者数は増えつづけています。特に鼻づまり(鼻閉)は最も厄介な症状で、睡眠障害を起こすなど患者のQOLを著しく低下させます。 放射線動物科学研究室の宮田佳奈さん(修士卒業生)らは、鼻炎が慢性化した患者さんやモデルマウスの鼻腔に高濃度に産生されている15-HEDEという脂質を見つけました。さらにこの15-HEDEが、鼻腔粘膜の血管を拡張して浮腫をおこし、鼻閉を起こす原因物質であることを、マウスモデルを使い証明しました。 この産生を抑えれれば、辛い鼻づまりを治す、花粉症の画期的な治療につながる可能性があります。 (CLOSE) |
| > 2021年 | |
| > 2020年 | |
| > 2019年 | |
| > 2018年 | |